ゲ ー ム 指 導 に つ い て by Tanaka
戻る
1指導者 2ゲームの導入 3ゲームのつなぎかた 4ゲームの変え方
5ゲームの作り方 6ゲームの指導法 7安全の守り方 まとめ
スカウティングはゲームである byB−P
スカウティング・フォア・ボーイズに刺激された少年たちがスカウティングを自発的に始めたが、
ついに は大人の援助を求めその人を隊長に迎え、隊が形成されたことにある。
B−Pの書いたスカウティング・フォア・ボーイズは早くいえばゲーム集である。
だが普通のゲーム集とちがうところは、ゲームを行うに当ってボーイスカウトの
「ちかい」と「おきて」を実践しながらやるというバックボーンがあることである。
B−P 「スカウティングの主旨の一つは少年の健康と体力を増進し、その人格を養うに役立つような、
チームで行うゲーム活動をさせることである。これらのゲームは面白く競争的であるべきで、
これによって勇気の本質、ルールに従うこと、規律、自制、鋭敏さ、不屈さ、指導性、
自分本位でないチーム精神などを仕込むことができる。」 (S・Mの手引 P69)
TOPへ
ゲーム指導法
1指導者
・指導者は、常に子供達から見え、子供達が見えるところに立つ。
・指導者が中心ではなく、子供たちが中心である。
・円になったとき、原則的に真中にいてはいけない。
・指導者のキャラクターを生かす。
・姿勢は、足を少し開いて両足に体重をかける。
・胸を張って、手は普通体の前で動かし、少々オーバー気味のほうがよい。
TOP
2ゲームの導入
・ゲームをよくする上で重要なポイントである。
・導入をうまくやれば、あとの進行は楽である。
・ゲームを行う前に、子供たちが、どんなことを考えているかを探り当てることが必要。
・それに関連したことから口にするとよい。
・ゲームには、偶然性、意外性が必要。
・それぞれのゲームは目的をもって行うが、子供たちには教えない。
・子供たちを受け身にまわしてはいけない。
・「こんなことをやってみようか。」などと誘いかけるようにする。
・初めから隊形を作るのでなく、自然と隊形ができるようにする。
・初めはそのままの状態でできるものや、近くの人とできるものを。
・子供たちに大きな声を出させることが導入の条件である。
TOPへ
3ゲームのつなぎかた
・ゲームは楽しいものだが、前後の関連性のないゲームをただ並べては、かえってつまらなくなる。
・人間の欲求にしたがって、ゲームを展開してゆくことが必要。(下図)
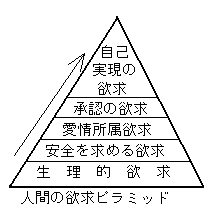
・ひとつのゲームから他のゲームに移すためのテクニックは大切。
・ゲームが流れるという表現が合うようにつなぐことが大切。
・ひとつのゲームだけを考えないで、2つ3つのゲームをセットしてゲームを考える。
・その組み合わせの中からつぎのゲームを考える。
・隊形をあまり変えないものを続ける。
・隊形を変えるときは、ゲームで変えたほうがよい。
・いつの間にか次のゲームに移ったという感じは、テンポを速くするので、子供たちに向いている。
・ムードを盛り上げるには、そのゲームが最高潮になる前にすぐ次のゲームに移る。
TOPへ
4ゲームの変え方
・一つのゲームでも、使い方によっていく通りにも生まれ変わる。
・ゲームの中に使われている名前や言葉を、その場の雰囲気にあったものに変えてみる。
・刺激になるものを変える。
・違ったゲームをつなぎ合わせてみる。
・ゲームのルールを変える。
・単純なものを複雑に、またはその逆。
・徐々に複雑にしてゆくこともよい。
TOPへ
5ゲームの作り方
・既製のゲームを覚えてゆき、新しいものを追ってゆくと、やがて行き詰まりを感じる。
・ゲームを作ることは大変なように見えるが、次のことを頭にいれてあたりを見まわすと良い。
・ゲームの多くは、人間の日常生活の活動のある部分を取り上げ、
それに時間、空間、機能に何らかの制約を加えてできている。
・一つの動作を取り上げ、いろいろな制約を加えるとよい。
○ゲームには一定の形式がある。
・形式は行動の方向を示す。
自分自身がやってみようと決心するのでなければ、いくら楽しいことでも満足はしない。
むしろ荷重を感じるかもしれない。 いかに動機づけるかは、リーダーシップによる。
・形式は社会性を教えてくれる。
ゲームは皆が協力しなければ、決して楽しいものではない。
協力することの意義や協力することの楽しさを、知らぬ間に学び経験させる。
○ゲームには一定の活動がある。
・身体を使う活発なゲーム、頭を使う静かなゲームなどどんなゲームにも一定の活動がある。
・ゲームはそれぞれの感情の表現や友情、あるいは嫌悪などを表す場として注目される。
・指導者は、一人一人の感情や人間関係を観察しながら指導できる。
・心の余裕を持つことが大切である。
○ゲームには一定の規則が必要。
・ゲームには定められた境界線を守ることや、順番を待つことなど一定の規則が必要である。
この規則を守ることにより、ゲームはより活発になりより楽しく秩序を保つことができる。
・これはまた社会性への訓練として大きな役割を果たすものである。
この規則をどのように生かすかは、リーダーの重要な課題である。
TOPへ
6ゲームの指導法
・指導者はいつもグループ全体に語らねばならない。
決して一人あるいは数人とでなく、また私的な会話は避けなければいけない。
・人数が多ければ多いほど少ない語で指導する。
○ゲームの説明と実施
・まずゲームの名称を紹介する。
・次に短く要領を説明する。
・さらに実地指導をやって見せる。
・簡単なゲームであれば、説明と同時に実演を加えてもよい。
・複雑なものや多人数の場合には、子供の一部を選んで実地指導をしてもよい。
・特に低学年の子供は、聞くことより見ることで学ぶことが多い。
・ゲームには人間の基本的な動作(柔軟性、器用さなど)を試すものが多い。
指導者は確実にできるように練習すること。
TOPへ
7安全の守り方
・ゲームをどんなに楽しくおこなっていても、誰かがケガをしたりすると今までのことが
全て無になってしまう。指導の始めから終わりまで絶えず気を使っていなければいけない。
・万が一にケガをした時は、あせらず適切な処置をする一方、それを教訓とするような
話し合いも必要である。
・あのゲームはあぶないからと消極的になってはいけない。
子供たちに危険を感じ取る力を付けさせるためにも、積極的にゲームをしなければいけない。
・どんなゲームにも必ず危険が伴うということを良く頭に刻みつけておく必要がある。
TOPへ
ま と め
ゲーム実施の16条
1.ねらい、目的を考えて、ゲームを選ぶ。
2.やる気を起こさせるような「導入の話」から入り、ルールの説明に移る。
3.ルールの説明は、わかりやすくはっきりとして、最後に質問があれば受ける。
4.くどくど口で言うより、リーダーがやって見せたほうがよいときもある。
5.ルールをきちんと守らせると共に、審判は公平で厳正に。
6.「静」と「動」のゲームを組み合わせる。
7.アウトになった者を長時間ほっておかない配慮が大切。
8.扱うゲームをよく消化してから、自信をもって実施する。
9.適当な時間で切り上げる。
10.安全について十分注意する。
11.夜間ゲームについては、特に事前の調査や計画に細心の注意を払うこと。
12.既製のゲームにのみ頼らず、応用と工夫により、自分のゲームを作るとよい。
13.全員が活躍できるものでなければならない。
14.施設、用具の点検を怠らない。
15.予備のプログラムを用意しておく。
16.新しいものと、古いものとを組み合わせる。
TOPへ 戻る